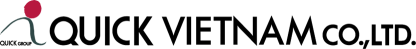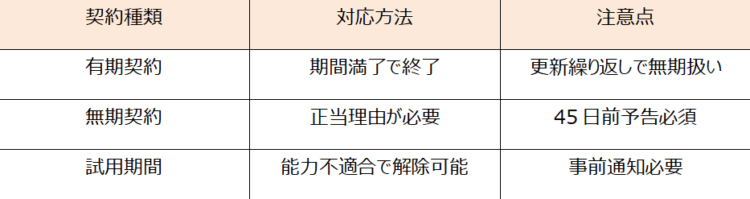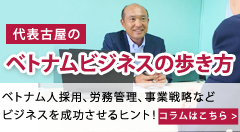公開日:2025/08/08
【組織開発】ベトナム現地法人での“強いチーム”をつくるには?
―異文化理解 × コミュニケーションで生まれる相乗効果―
◆ はじめに:多様性が強みになる組織づくりの鍵とは?
活力ある若い労働力と急成長する市場を背景に、多くの日本企業がベトナムに拠点を構えています。しかし、採用・配置・育成といった人材戦略が、日本と同じやり方では機能しないという声を多く伺います。
現地の組織は、以下のような特徴を持ちます:
・平均年齢が非常に若く、キャリア志向が強い
・家族や地域との結びつきを重視し、転職への抵抗感が少ない
・指示待ち型の傾向がある一方で、自己主張はしっかりしている
・上司への敬意は強いが、内心で不満を持ちやすい(表面に出にくい)
このような環境で、日本流のマネジメントをそのまま持ち込んでも効果が出づらく、むしろ摩擦の原因になることもあります。
本コラムでは、ベトナムという異文化環境において、日系企業が現地人材の力を最大限に引き出し、「チーム」として機能するための実践的なアプローチをご紹介します。

【ポイント1】異文化理解を“前提”にする:摩擦から協働へ
● ベトナム人社員の価値観と行動特性
・間接的な表現を好む(沈黙や遠回しな言い回しが多い)
・年長者・上司に敬意を払う文化(発言を控える傾向)
・「恥をかかせない」ことが重要視される(批判はNG)
✅ 異文化理解学習のすすめ
| 内容 | 狙い | ベトナム的ポイント | 補足 |
| ベトナム文化理解 | 現地人材の価値観や行動傾向を学ぶ | 上下関係の重視、対立回避、間接表現の傾向 | 日常業務の中で起きる“違和感”の正体を明確化し、相互尊重の土台を築く。 |
| 日本文化の紹介 | 日本の仕事の進め方や職場マナーを共有 | 報連相、PDCA、定時厳守などの背景を説明 | 日本流の期待や価値観を“理不尽”ではなく合理的と納得してもらうためのステップ。 |
| ワークショップ | ケーススタディやロールプレイ形式で体感 | 問題を「自分ごと化」しやすい | 座学ではなく実際の行動に結びつくよう、現場の事例をテーマに設計することがポイント。 |
【ポイント2】ルールの明文化で“思い込みのズレ”をなくす
✅ 明確にすべきコミュニケーションルール
| 項目 | 明確化すべき点 | ベトナム人の傾向 | 補足 |
| 会議運営ルール | 発言順/司会の役割/議事録の扱いなど | 上司の前で自由に発言しづらい文化 | 「誰でも自由に」ではなく、「順番に意見を聞く」形式のほうが実効性がある。 |
| 報連相の運用定義 | 報告・相談の内容/頻度/ルートの定義 | 問題を抱え込みがち、遠慮しがち | 「相談したら叱られる」という誤解を防ぐため、相談行動の評価”も明示する。 |
| 情報共有の形式と頻度 | チャット/共有ドライブ/進捗会議など | チャット文化には慣れているが、報告形式はばらつく | 若手でも理解しやすいフォーマットを作成し、全員に周知・徹底する必要がある。 |
【ポイント3】ベトナム人材の“感情”に寄り添う関係づくり
✅ 信頼関係を高める交流機会
| 活動例 | 内容 | ベトナム的文化背景 | 補足 |
| 祝日や文化行事との連動イベント | テトや女性の日に社内イベント | 家族・感謝・敬意の文化 | 形式的なイベントではなく、感謝やつながりを意識した演出がポイント。 |
| 雑談や昼食会 | 非業務の対話の場を設ける | 本音を職場で出しづらい傾向 | 「気軽に話せる環境」が心理的安全性を高め、相談行動にも繋がる。 |
| 感謝・称賛の文化 | サンクスカード・表彰の導入 | 外向的・感情表現が豊か | 若手社員の“見てもらえている感覚”がエンゲージメントを大きく左右する。 |
【ポイント4】「自分ごと化」させる目標設定と役割分担
✅ 納得感を引き出す設計ステップ(+補足説明)
| ステップ | 内容 | ベトナム人材の反応 | 補足 |
| 共創型目標設定 | メンバーと目標を一緒に設計 | 意見が反映されることでやる気が出る | 参加型プロセスを通して、目標を“自分のこと”と捉えやすくなる。 |
| 強みに基づいた役割設計 | スキル・志向に合わせた担当 | やりがい・成長意欲が高い傾向 | 無理なジョブローテーションより、得意分野への集中が効果的。 |
| 定期共有と称賛 | 進捗・貢献を“見える化”する | 成果を認められたい意欲が強い | 数値成果だけでなく、プロセスや工夫を承認する仕組みを入れると効果的。 |
【ポイント5】リーダーは“指示型”から“問いかけ型”へ
✅ 管理職に求められるスキル
| スキル | 内容 | 異文化対応上の理由 | 補足 |
| 問いかけ型コミュニケーション | 指示より質問で考えを引き出す | 指示待ち・沈黙を破るために有効 | 「どう思う?」という習慣が部下の思考を促す。まずは“待つ力”が鍵。 |
| 合意形成のファシリテーション | 意見の整理・調整・合意形成 | ベトナム人は対立回避傾向 | 「皆が納得している」プロセスを通すことで、意思決定後の実行力が増す。 |
| 非言語対応への配慮 | 表情・間の取り方に注意 | 無表情=怒っていると捉えられる | 「笑顔で聴く」「うなずく」など、非言語での安心感が信頼につながる。 |
◆ まとめ
ベトナムにおける効果的なチームビルディングは、単なる親睦を深める活動に留まらず、異文化理解の促進、円滑なコミュニケーションルールの確立、そして共通目標へのコミットメントを高めるための戦略的な取り組みです。
本コラムでご紹介したアプローチを継続的に実行することで、貴社のベトナム事業は、多様な人材の力を最大限に引き出し、持続的な成長を遂げることができるでしょう。本コラムが、貴社のチームが抱える課題を解決し、さらなる発展を後押しするためのヒントとなれば幸いです。